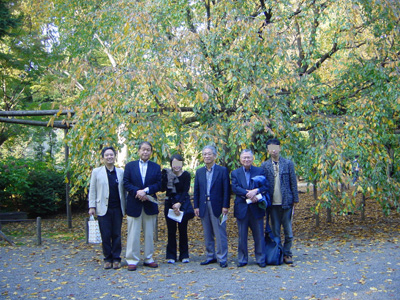since 05.02.08
本日のお題
--- today's theme
元禄14(1702)年3月14日江戸城松の大廊下。
播州赤穂浅野内匠頭長矩が、高家筆頭吉良上野介義央を斬りつけた赤穂事件は、浅野の即日切腹・領地お取上お家断絶で幕を閉じたように思えた。
しかし――。
赤穂に仕えていた藩士達は当時二百数十名。藩論は揺れた。恭順開城か、籠城戦闘か、殉死自決か。やがて4月19日、傍目には城収使龍野の脇坂淡路守一行に対し、大手門は何の抵抗もなく開かれた。傍目には恭順の姿勢、他のお取り潰し藩と何ら変わりのない収城の光景である。
「吉良仇討ち」という、今一つの決断を隠したまま……。
播州赤穂浅野内匠頭長矩が、高家筆頭吉良上野介義央を斬りつけた赤穂事件は、浅野の即日切腹・領地お取上お家断絶で幕を閉じたように思えた。
しかし――。
赤穂に仕えていた藩士達は当時二百数十名。藩論は揺れた。恭順開城か、籠城戦闘か、殉死自決か。やがて4月19日、傍目には城収使龍野の脇坂淡路守一行に対し、大手門は何の抵抗もなく開かれた。傍目には恭順の姿勢、他のお取り潰し藩と何ら変わりのない収城の光景である。
「吉良仇討ち」という、今一つの決断を隠したまま……。
幕府から見た赤穂事件
| 殿中にて鯉口三寸切れば切腹―― 浅野内匠頭は死を覚悟してその禁を犯したと言える。しかし吉良上野介を殺害すること叶わず、喧嘩両成敗の原則に反して吉良に対するお咎めすらも無かった。城中での刃傷事件としては異例な裁断を行った幕府の見解とは、将軍の思いとは如何様であったか。 側用人・柳沢吉保から事の次第を告げられた天下の将軍・徳川綱吉は激怒した。「大事の勅使饗応の日の失態、お廊下を血で汚された」と。即断即決よりも今一度くらいの詮議はした方がいいのではないか、そんな周囲の意見に耳も貸さない。むしろ、それら意見も真に抗議を申し立てるのではなく、あくまで苦言の一つ、結局は将軍の決議に落ち着いてしまうのだ。綱吉の君主権限の大きさがそこに現れていた。 「余は生まれながらの将軍である」そう公言した三代家光と違って、五代綱吉は覇権争いに絶えず気を揉む生涯であった。家光の四男として生まれた綱吉には、元服まで健やかに育った兄が二人いた。世子・家綱、そして二つ年上の綱重である。父も長兄・家綱も弟二人を平等に扱い、寛文元年(1661)閏八月九日、綱重は甲府に、綱吉は館林に、それぞれ同分二十五万石を与えた。綱重18歳、綱吉16歳。 綱重と綱吉は、待遇もほぼ同格であったことから、兄弟としては反目する間柄ではなかったと言われている。問題はその母たちだった。綱重生母のおなつの方は京都の町人弥一郎の娘、お玉の方は賀茂の神職を父とするがそれは母親の再婚先で、実父は京都堀川通り西藪町八百屋仁左衛門。二人は似たような境遇に育ち、年もさして変わらず、それ故家光の寵愛を争っていつも火花を散らしていた。 もしも家綱に嫡男が生まれていれば、次兄・綱重が病没することがなければ、綱吉は館林の大名のまま終わっていた。だが、それは起こった。 お玉の方(家光病没後出家、桂昌院)にとってそれはまさに、天から舞い降りた神仏の贈り物のような心持ちがした。我が子が、八百屋の娘である自分の産んだ子が、天下の大将軍におなりになるかもしれない――期待は大いに膨らむ。 当時下馬将軍と呼ばれ権力を握っていた大老・酒井忠清は鎌倉の故事を持ち出して有栖川宮擁立をはかるが、老中堀田正俊の強い反対にあって失敗。こうして綱吉はめでたく五代将軍となり、酒井は失脚、堀田が台頭する。これら幸運に恵まれ、元々信心深かった桂昌院はさらに神仏への傾倒を深めていった。それは、いつ脅かされるかも知れない権力への執着であり、桂昌院の焦りでもある。月日を経るごと神仏観が狂言的になっていく母に、綱吉はただ従い、生涯彼女に頭の上がることはなかった。 それでも初期は「天和の治」と称される政治手腕を発揮していた綱吉だったが、堀田正俊の刺殺事件によって側用人制が導入されたことで、やがて信頼する家臣へのあまりの贔屓、またのちに発布される「生類哀れみの令」を経て、次第に「犬公方」と揶揄される悪政に変わっていく。元禄改鋳によって一気にバブルになった経済、熟れすぎた元禄文化、異常な法令による民衆統制。それでいて周囲は皆権勢にすがろうとする者ばかりで、命を掛けての嘆願、主君の諫めを行う者もいない。綱吉の専制政治はまさに絶頂を極めていた。 「母上に、叙位を」そんな綱吉の母を思う心から、元禄13年末、吉良上野介を京都に送った。名目は勅使への年賀の挨拶。吉良の努力もあって、「どうか母に地位と誉まれを」という綱吉の願いが、ようやく聞き届けられようかという時期に入っていた。此度の返礼の使節接待には内密にその方面の話もあるであろう。綱吉は朝廷からの朝賀返礼の使節を、期待に胸膨らませて待っていた。饗応役には伊達と浅野。浅野は一度役に就いた経験もあるし、万事穏やかに運ぶであろう……そんな考えが綱吉にもあったかもしれない。 そして起こった、松の廊下刃傷。 「何と斯様な失態にて将軍の顔に泥を塗りおるか!」綱吉の怒りはすさまじいものだった。誰も、恐れ多い将軍のご意向に背く者はない。まして実母桂昌院への叙位を求めて交渉に当たらせていた吉良に咎めを与えるなど、進言したところでできようはずもない。五万石の小国一つ、消えたところで大差あるまい、今までも改易は多くあったこと。そう納得した。これが一年半の時を経て江戸を揺るがす大事件になろうとは、誰も想像することはできなかった。赤穂の討ち入りを知った綱吉は大いに動揺し、自分の決断を悔いたとされているが、実際のところは思いもかけぬ反乱に相当の焦りを抱いたことだろう。 綱吉はその後嫡子の産まれることもなく、64歳でこの世を去る。嗣いだのは、皮肉にも次兄・綱重の遺子で若年にして当時将軍になれなかった、甲府藩主・徳川綱豊(家宣)。長きに渡る利権争いの末の就任だった。 |
柳沢吉保と徳川綱吉、そして吉良上野介
| 18歳で当時館林藩主だったのちの征夷大将軍・徳川綱吉の小姓となった柳沢吉保はその寵愛を受け、綱吉の将軍就任後は出世を重ねて側用人という地位に上り詰める。 その後1万2千石の大名になったのを皮切りに度々加増されて、ついには甲府藩15万石を与えられるまでになった。甲府はそれまで徳川一族が支配してきた領地でありこれは異例のことであった。また吉保の「吉」の字は綱吉から戴いたもの、さらには徳川氏の旧姓である松平の姓を名乗ることも許されている。 綱吉の寵愛も異常で、綱吉は柳沢邸に58回も出かけていったと言われている。噂ではそのうちに、柳沢の愛人・染子に手を付けたので、柳沢の一子吉里は実は御落胤であるという。柳沢が相次ぐ石高の加増になったのもそのため、そしてやがて綱吉がただ一人の実子吉里を世継ぎにしようと考えたので、それを阻止するために正室鷹司信子が綱吉を刺し殺して自らも自害した、などという話までまことしやかに囁かれた。真偽のほどは定かでない。綱吉の死には色々と曰くがある。 刃傷事件の起きた元禄時代、柳沢は大老に匹敵するほどの権勢を誇っていた。幕閣の意見をはね除け綱吉の意を酌んで浅野に切腹を命じたのも柳沢である。柳沢と吉良には密接な関係があった。それというのも、綱吉の母・桂昌院が女性として最高位の従一位に叙せられた時、柳沢の采配の元、朝廷へ莫大な贈り物をしたという背景がある。これに吉良は協力をしていた。赤穂事件のそもそもの発端、勅使饗応もそのための根回し。吉良が京へ上ったのは贈位の目論見があったからだった。そのため両者の間は昵懇になり、赤穂事件で当初お咎めがなかったのはそのせいではないかとも囁かれた。もしここで吉良を討ってしまえば、桂昌院贈位の計画は泡と消える。結局吉良は討たれることになるが、それより前の元禄15年三月、桂昌院は無事従一位に叙せられた。将軍権威が命令を絶対化させ、幕府の沙汰を贔屓目にさせたとも言えなくはない。 |
本日の道順
--- today's course
| JR駒込駅 ↓ ①六義園 ↓ ②藤堂家棟門 ↓ ③西福寺 ④染井稲荷神社 ↓ ⑤染井霊園 ↓ ⑥本妙寺 ↓ ⑦巣鴨地蔵通り商店街 ↓ ⑧高岩寺 ↓ ⑨真性寺 ↓ JR巣鴨駅 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ここから先は、時間の都合上立ち寄れなかった巣鴨の史跡です。 お時間ある時にでもお立ち寄り下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
以上、お疲れさまでした~(・_・)(._.)
ブラウザを閉じてお戻り下さいませ。
Copyright c 2005 奴娘町長屋 all
rights reserved. 無断転載禁止。 Designed by TG